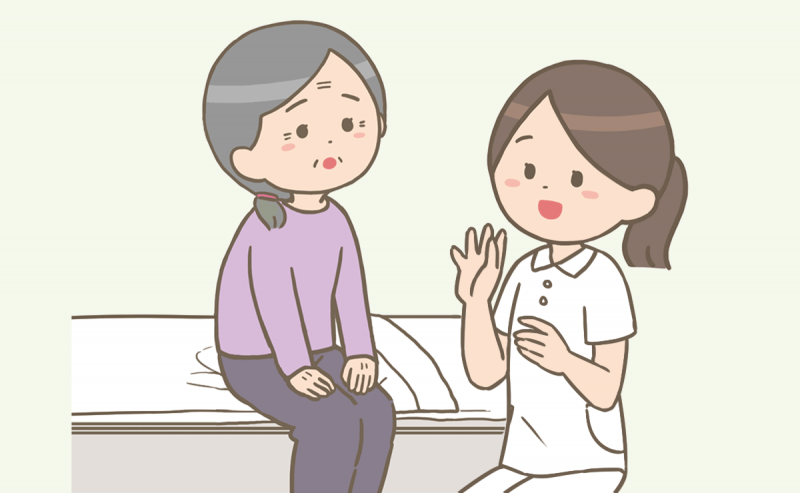記事公開日
睡眠障害の症状は「眠れない」だけじゃないって本当?

睡眠障害でお悩みですか?睡眠障害はただ眠れないだけでなく、さまざまな症状があり、放置していると取り返しのつかない事態を招く恐れがあります。
また、睡眠障害の原因には別の疾患が隠れている恐れもあるため注意が必要です。
そこで今回は、睡眠障害が引き起こす問題やどのように解決すればいいのかについて詳しく紹介します。
睡眠障害とは?
眠れない
「睡眠障害」とは、睡眠に問題がある状態をいいます。ただ単純に眠れない=睡眠障害ではありません。
眠れなくなることはよくみられますが、これは環境や生活習慣、精神的・身体的な病気などいくつかの要因が重なって起こることが多いです。
睡眠障害というと「眠れないこと」と考えがちですが、眠れない以外にも様々な症状があります。
よく眠れないと眠気やだるさ、集中力低下などを引き起こしますが、睡眠の問題やそれに伴う支障が1ヶ月以上続く場合は何らかの睡眠障害にかかっている可能性が考えられます。
睡眠に何らかの問題がある状態を指す
先述した通り、睡眠障害とは睡眠に何らかの問題がある状態を指します。代表的な不眠の他、就寝時の異常感覚なども睡眠障害の一つです。
睡眠障害の症状や原因は後述しますが、睡眠障害が長期間持続するとうつ病や生活習慣病などになりやすくなるので注意が必要です。
睡眠障害によって日々の生活に支障をきたすこともあるため、早期発見かつ睡眠障害を適切に対処することが重要と考えられています。
精神疾患に伴うものが多い
- うつ病
- 統合失調症
- 双極性障害
- パニック障害羅列:不安障害
- PTSD
精神疾患とは、脳の機能的な障害や器質的な問題によって生じる精神的な疾患の総称で、代表的なものとしてはうつ病や統合失調症が挙げられます。
このような精神疾患に伴い、「眠れない」「睡眠中の異常行動」などの睡眠障害が出ることが多いです。
逆に、睡眠障害が長期間持続することでうつ病や生活習慣病など他の病気につながることもあります。
睡眠障害にはどんな症状がある?
自覚症状
・不眠
・過眠
・就寝時の異常感覚
・睡眠、覚醒リズムの問題
はた目から見た症状
・いびき
・無呼吸
・睡眠中の異常な行動や運動
自覚症状とはた目から見た症状があります。寝つきが悪く熟睡できない、途中で起きてしまうといった不眠は日中の過剰な眠気につながります。
適切な時刻に入眠できず、希望時に起床することができないというように、睡眠リズムが乱れることもあります。就寝時の異常感覚には、脚もむずむず感や火照りが挙げられます。
周囲の人から指摘される睡眠中の異常行動には、寝ぼけ行動、寝言、睡眠中の大声・叫び声などがあります。
睡眠障害の原因にはどんなものがある?
環境要因
・引っ越し・入学・就職
・季節の変わり目
・寝室の温度や温度
・騒音や光 など
身体的な要因
・高血圧
・糖尿病
・アレルギー疾患 など
精神的要因
・人間関係の悩み
・不安やイライラ
・うつ病などの精神疾患 など
生活習慣の要因
・入眠前のネット利用
・アルコール
・喫煙
・カフェイン摂取過多 など
睡眠障害の原因を挙げると、大きく4つに分けられます。睡眠障害はその原因によって治療法も異なるため、まずは睡眠の問題を把握しておくことは重要です。
精神疾患からくるものなのか、生活習慣が原因なのか、適切な治療を受けるためにも自分の睡眠状態をチェックしてみましょう。
もちろん複数の要因が複雑に絡んでいることもあります。早めに専門機関に相談するのも一つの手です。
自分でできる睡眠障害のセルフケア
呼吸だけに意識を集中して思考を止める
気分が落ち着かず、さまざまな思考が出てきて覚醒してしまう時は、呼吸だけに意識を集中して思考を止めましょう。
呼吸に集中することで、心が落ち着き、リラックスすることができます。また、呼吸は脳に酸素を送り、血流を改善する効果もあります。
ストレスや不安がある時は特にネガティブな感情が出てきやすいですが、呼吸だけに意識を集中し、ネガティブな感情を受け流すようにしてみてください。
夕食は交感神経を刺激する食べ物を避ける
交感神経を刺激する作用がある食品を避けるのも一つの手です。交感神経を刺激する作用がある食品は、寝つきや眠りの質が悪くなる原因になります。
例えば、香辛料のトウガラシやコショウ、カフェインが入っているコーヒーや緑茶などです。
アルコールが代謝されてできるアセトアルデヒドにも覚醒作用があり、睡眠の質を低下させてしまうため寝る前の飲酒も控えるといいでしょう。
就寝前にスマホをチェックしない
寝る前の「スマホ」にも注意しましょう。人間には自然な睡眠を誘うメラトニンというホルモンがあるのですが、スマホの光によりこのメラトニンの分泌量が抑制されます。
メラトニンの分泌量が抑制されることで寝つきが悪くなってしまうのです。新しい情報や見た映像によって脳が刺激を受け、寝つけなくなることもあります。
眠くなるまでの時間つぶしについついスマホを触ってしまうかもしれませんが、良質な睡眠のために就寝前はスマホを見ないと決めましょう。
睡眠障害を治療する方法は?
睡眠改善指導
不眠症状に悩まされる場合、「寝床=眠るところ」として再学習したり、同じスケジュールを守るなどして睡眠の習慣をつけるように訓練していきます。
例えば、15分経っても眠れない時は寝床から出てリラックスできることをし、眠気がきたら寝床に戻ることを繰り返します。
睡眠に関する悩みを解消する睡眠アドバイザーも活躍しているので、医療機関をはじめ、専門家に相談することで睡眠障害の改善につながるでしょう。
リラクセーション法
リラクセーション法とは、身体の一部分に力を入れて緊張させ、力を抜く体操です。副交感神経系のはたらきを優位にさせ、リラックス状態を作ることで安眠モードに導きます。
特に、寝る前や夜中に起きてしまって眠れない時に行うと効果的です。
睡眠障害の相談はどこでできる?
日本睡眠学会の睡眠医療認定医
日本睡眠学会は睡眠科学と睡眠臨床に関する科学的知識を、国民や医療機関の方々に広く提供することを目的として開設されています。
睡眠医療の普及と向上を促すことを目的としており、睡眠医療認定医には豊富な知識や経験があります。
睡眠障害でお悩みなら、睡眠医療認定医が常駐するお近くのクリニックを検索し、足を運んでみるといいでしょう。
精神科医
精神科は「こころの病気(精神疾患)」を診る医療機関です。精神医学を専門とする医師に相談するのもいいでしょう。
睡眠障害は精神疾患を伴うケースも多いですが、専門性の高い精神科で検査を受けることで適切な治療ができます。
精神科では精神疾患の検査・治療ができるので、睡眠障害以外の問題や病気などが見つかることもあります。
精神科訪問看護を頼るという選択肢も
精神科訪問看護とは?
対象者
・精神科・心療内科に通院中の方
・精神疾患の診断を受けた方
・診断がなくとも医師が必要と判断した方
東京精神訪問看護ステーションのご紹介
東京精神訪問看護ステーションでは、精神科に特化した訪問看護を提供しており、適応障害の患者さんに対しても、一人ひとりの状態に合わせた訪問看護を提供しています。
看護師や精神保健福祉士などの専門スタッフがご自宅に伺い、日常生活のサポートから心のケアまで、様々な支援を包括的に行います。
ご本人だけでなく、ご家族の皆さまも安心して療養生活を送れるよう、様々な角度からサポートいたします。
訪問範囲
世田谷区 杉並区 渋谷区 中野区
※その他の地域の訪問看護についてはお問い合わせください。